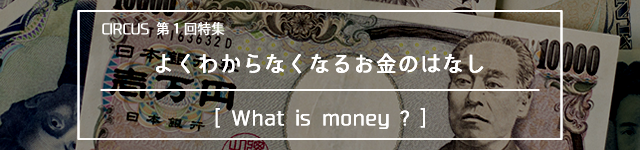なくなりそうでなくならないクラシック音楽
なんか暗い話になってしまった。
ここまで読んで、音楽家を志そうとしていたのに、回れ右をしようと思った人がいたのならちょっと待ってほしい。
ちょっと明るい話だってあるのだ。
昨年末の野村総合研究所の記事だが、「人工知能やロボット等による代替可能性が低い100種の職業」の中に、音楽教室講師、クラシック演奏家、作曲家、声楽家など、クラシック音楽関連の職業が4つも入っている。
https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx
どうやら、クラシック演奏家という職業はなくならないらしい。
自動演奏ピアノや、バイオリンを弾くロボットは既に存在する。
トヨタ産業技術記念館のロボット
https://www.youtube.com/watch?v=NFX33EmkAVc
ロボットはミスもしないだろうし、音程も外すことはない。羨ましい限りである。でもその演奏は、まだまだ生きた人間の演奏家の領域を脅かすほどのものとは言い難い。
ああ、よかった。ちょっとほっとする。
生の演奏会というのも、なくなりそうでいて、なくなることはないだろう。
確かに高いお金を出して、遠くの会場にわざわざ足を運ぶよりは、家でCDやインターネットでコンサートを視聴したほうが、安いし、快適だ。ソファに寝ころんで、おやつを食べながら名門オーケストラの演奏会を聴くことができるし、飽きてしまえばいつでも切ってしまうことができる。
でも、ライブにはライブにしかない雰囲気がある。
演奏会に行くから、と、お気に入りの服と靴を身に着け、ホールの近くでちょっと美味しいものを食べてから、クラシックの生のサウンドを聴き、休憩時間にはシャンパンを飲み、たった今聞いた演奏の感想を語り合う、といった全ての一連の行動が、コンサートを聴きに行くかけがいのない「経験」(ドイツ語ではErlebnis「エアレーブニス」と言ったりする。)なのである。
音楽そのものだって、ライブはCDのように修正されていないから、ミスや事故が起こることもある。でも、音楽の流れ、うなり、渦、そういうものは、ライブでしか絶対味わえない。強く心に訴えかけてくるものというのは、ライブにしかない音楽家たちの魂だったり、奏者と聴衆の一体感だったりするものなのだ。
日本のクラシック音楽の未来
首都圏と地方では状況も違うと思うが、日本のクラシック音楽の聴衆は年配の方が多い。舞台の上から客席を眺めても、それは一目瞭然だ。
無理もない。クラシック音楽のコンサートに行くには、お金と時間と興味がいる。そして、お金と時間があるのは、若者でなく、大抵年配の方々なのである。
その点ヨーロッパでは、若者が気軽にコンサートを訪れることができる環境である。ヨーロッパのコンサートホールやオペラハウスの多くには立ち見席が設けられていて、そのチケットは500円ほどで手に入るのだ。レストランでワインを飲んでいる若者が、「あ、今日のオペラ面白そうじゃない?ちょっと見に行こうよ。」なんて言って、ふらりと立ち寄れてしまう環境なのである。
日本のコンサートホールにも、安価なチケットの立ち見席があれば若者の聴衆が増えるのに!と思うのだが、きっとそうもいかない理由があるのだろう。つくづく残念である。
厳しい状況の中、それでも何とか育まれ続けているクラシック音楽という文化が、これからも切り捨てられることなく、何百年後にも存在し続けてくれることを祈らずにはいられない。もちろん、そのためには私たち音楽家もサポートされっぱなしではなく、サポートして良かったと思われるようなアクションを起こしていかないとだめなのだろう。
クラシック音楽の生き残り、というテーマについてCIRCUSマガジンの編集の方と雑談になった時、「そもそもオーケストラの人数が多すぎなのでは?ポップスやジャズバンドは4人くらいの編成が平均的だが、オーケストラはコストパフォーマンス的に小編成のバンド以上の価値を提供できているのだろうか」「弦楽四重奏などの少人数編成での公演を基本にしたり、その方向でクラシック音楽が今後発展していくべきなのでは?」という質問があった。
うーん、なるほど。理にかなった意見である。
でも、このアイディアは、現実的にはなかなか難しいだろう。
オーケストラの曲は、オーケストラの編成で書かれているので、それを弦楽四重奏版などにしてしまうと、どうしてもショボくなってしまうのだ。
学生の時に、結婚式でバイオリンソロを弾くというアルバイトを引き受けた。その時会場でお客様に「スターウォーズ弾いてください」とリクエストされて、凍り付いたことがある。バイオリン一本でスターウォーズのテーマなんてほぼ罰ゲームだ。あれは、フルオーケストラの編成だから迫力があってカッコいいのだ。楽器を演奏しない人には、え?なんでダメなの?と思われてしまうかもしれないが、こちらからすれば、「玉ねぎ一個でカレー作ってね☆」と言われてるようなものなのである。
ごく僅かな人数のみ、生の楽器で演奏させて、あとはシンセサイザーなどで音の厚みを補強するなどして人件費を抑える、ということをやっているミュージカルの劇場なり録音は実際多い。しかも、気を付けて聞かなければそれがコンピューターの音源だと気づかない人も多いのではないか、と思うくらいその技術は発達している。コンピューターの音源の発達は、我々生きた音楽家の働く場所を確実に脅かしている。
昔は、無声映画に生のオーケストラがついていて、映像に合わせて音楽を演奏していた、ということもあった。まるでオペラである。当時の映画音楽演奏家たちはベルリンフィルよりも儲けていたらしい。今は映画音楽と言えば、すべて録音である。
こういうのを見ていると、音楽においても予算という問題で、淘汰された、または淘汰されゆく分野というのが存在しているのだなあ、ということが実感できる。
かといって、経費削減という意味で、クラシック音楽が弦楽四重奏など、人数の少ない室内楽の編成で発展していくということもないだろう。基本、マイクで音を増大させることのないクラシック音楽では楽器の数が少ないということは、音量や音の厚みも少なくなるということだし、楽器の種類が少ないということは、使える音色も少なくなるということだ。これでは、表現できることが本当に限られてしまうだろう。
クラシック音楽は保護されるべき伝統芸能?
生き残りのために進化しない、または淘汰されないクラシック音楽は「伝統芸能」という区分において、守られていくべきなのだろうか。
私たちはクラシック音楽における時代を語るときに、「バロック時代」とか「古典」、「近現代」なんて区分をしたりする。でもそれらの曲は当時、全てが「現代曲」だった。
モーツァルトのオペラなんて言ったら、「そんな高尚なもの、勉強して行かないと見れないよ。」と尻込みしてしまう人も多いのではないかと思うが、まあ一度見てみてほしい。内容は不倫や恋愛のドタバタ劇がほとんど。当時の人たちにとって、新作のオペラは、新しい昼ドラや月9の新シリーズのようなものだったと思う。当時テレビという媒体がなかったから、劇場でオペラという形をとっていただけの話だ。人間が好んでそういったエンターテイメントを求める本質は、時代が変わってもそう変わらないものなのだ。
モーツァルトやベートーベンは過去の人なので、もう新作は生まれない。私たち演奏家は、彼らの既存の作品を繰り返し演奏するだけだし、聴衆はストーリーもエンディングもわかっている、何度も繰り返し聞いたおとぎ話を聞くように、その音楽に耳を傾けるのみだ。
それではクラシック音楽がやはり、博物館に鎮座するような「伝統芸能」なのかというと、私はそうするべきではない、と思っている。
私がクラシックの曲を演奏するときは、当時の楽器がどのようなものだったのか、どんな奏法が存在していたのか、どういう風に弾かれることが好まれていたのか、などを踏まえて演奏する。
でも、踏まえたうえで、敢えて現代のコンサートホールの音響に見合うように弾いたり、現代の人の耳に不自然になりすぎないように弾いたりする。私たち音楽家の使命は、当時の音楽を完全に再現する、ということにこだわることではなく、聴衆の心に何かを訴えることだと思うからだ。
クラシック音楽は、そうやって現代に生きる音楽家に演奏されることによって、博物館の飾り物に留まるのではなく、生き生きと現代に響きわたることができるのではないか。
お金とクラシック音楽
音楽はどこから生まれたのだろう。
人の心から湧き上がる情熱や鼓動がリズムとなり、儀式や祭りに太鼓が使われるようになった。神様への祈りが歌となり、その歌の厚みを補うために楽器が使用されるようになった。
音楽は、内から外へと流れ出る私たちの感情そのもので、本来はお金とは繋がりがないものだった。
やがて音楽は教会のミサに用いられるようになる。これがクラシック音楽の先祖だ。
そして音楽家達は、教会や王侯貴族に雇われて、教会のミサや、宮廷の催しもののために音楽を書くようになった。音楽家という職業が生まれ、お金に振り回されだしたのはこの頃からだ。
モーツァルトの活躍する時代がやってくると、音楽家はただ雇わるのみでなく、自身の楽譜を出版したり、コンサートを催したりしてお金を稼ぐようになった。フリーランスの音楽家の誕生だ。特に多額のお金が動くオペラの成功に、音楽家達は一喜一憂した。まるでドラマの視聴率に一喜一憂するプロデューサーのようだ。
この頃から作曲家たちは、自分の芸術性を証明する「書きたい曲」と、「売れる曲」の間で悩むことになる。一銭にもならないが、自分の書きたい曲を書くか、聴衆に媚びた売れる曲を書くか。
こういった悩みは、作曲家や音楽家だけに留まらないし、今も昔も全く変わらない。
お金というシステムは、人類にしかないすばらしい発明だ。
そのシステムはとんでもなく強大で、そのせいで生まれる可能性や育つ可能性のあった芸術作品や文化が、息絶えてしまったことがあるのも事実だろう。でも、その力がなければ生まれなかった芸術作品も数多くあったはずだ。
クラシック音楽の生き残りも、このシステムとの共存にかかっている。美しいものや良い物、芸術性の高い物だけが、このシステムに気に入られるわけではないというところが、また難しいところである。
芸術作品は、お金というシステムに気に入られなければ日の目を見ないことも多いが、マネージメントのみが優秀なため売れるような、中身のない演奏を迫られるのは、私たち音楽家にとっては地獄である。
クラシック音楽自体が完全に衰退、または消滅することはないだろう。それは既に何百年も淘汰されずに生き残ってきたものだし、これからもそうやって生き続けていくと思う。それが細々とでなく、華々しくあるためには、芸術も、人類に今や深く根付いたお金というシステムと賢く付き合っていく必要がある。
お金というテーマを扱う時、私たちの間には何故だか生々しいとか、いやらしいといった妙な罪悪感が生まれることがある。(それが原因で音楽家をはじめとする芸術家は、暗にタダ働きを求められることが多い。)しかし、お金というシステムも人類が生み出した文化の一つと考えてみると、クラシック音楽とお金という一見対極にありそうな関係が、同じ文化同士、互いに尊重し合いながらうまく共存していけるような気がする。
ただ一つ忘れたくないのは、お金というシステムに魅入られることがなく日の目をみなくても、ひっそりと強く美しく、心を動かすものは確かに存在していて、そういうものを知ってたり、持っていたり、大切にしていたりすることはとても素敵なことだということである。
それは、お金やクラシック音楽が生まれる以前の、とても原始的な、私たち誰もが心の中に持っている宝石のようなもの。その輝きや温かさを見失わないように気を付けたい。さもないと、お金というシステムは、あっという間に私たちを飲み込み、奴隷にしてしまう力だって持っているのだから。