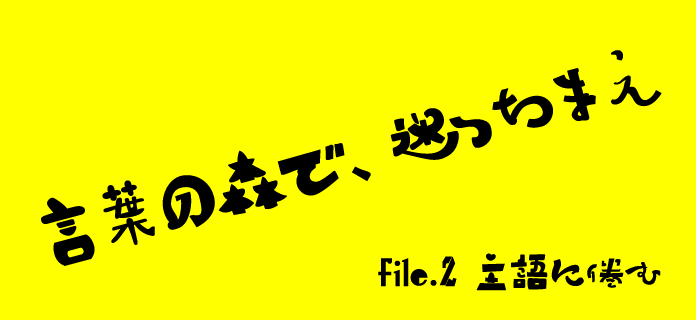男の子になりたい時期があった。
11~12歳頃がピーク。
小学生女子の登校風景はスカート+襟にフリルなんかのついたブラウス…が圧倒的多数の時代、自分はひとりジーンズにシャツ、登校帽の伸びきったゴム持って振り回し、ランドセルはだらんと右肩片方掛け、上履きの踵は踏んで平らに、校舎内をずるずるひきずり斜めに歩いていた。異様に広い校庭、塀の外はどこまでも続く田畑と点在する住宅。はっ。
で、SFを読んでる。
登場人物の名前をエヌ氏、エス氏などと書く。
作者はそれを「通俗性の排除」と説明していたし、エヌやエスどころか「男」としか書かぬことも…どころかそのドえらくショートな短編の中にろくに主語が出てこない例も多い。通俗性の排除、乾いた無名性。いいじゃない。
もし「ひとりの男が歩いていた。」とあれば、はいよ了解と読み飛ばし次の文節へ行くであろうわたくし。観劇の場で舞台にふらりと役者が出てきても誰も驚かん、通俗性の排除、乾いた無名性、ひいては普遍性。
しかしだ、ふとそれを「ひとりの女が歩いていた。」と変換してみてワァびっくり。ちっとも読み飛ばせぬ、むしろ心ざわつき、立ち止まるだろう。
「女」には「男」という言葉の何気なさ・無名性がないじゃないか。
あらかじめ通俗臭ぬんぬん薫き込み、通りすがりだしマア気にせんでくれ…という記号には決してなり得ない、それが「女」なのだ…と、生まれて初めて思った瞬間です。
そんじゃ女という単語なしに、女が道を歩いてることを、気負いなく説明できないのか、できんのだ。「身体つき丸みを帯びた人が」(丸いとは限らん)「髪の長い人が」(男も長い場合もある)「男ではない人が」(じつに卑屈だ!)。
そもそも男と書いた時はその顔のない無個性のために、説明にすらなっていないところに最大の利点があるので、説明せんければならぬ時点でもうすでに、サラリと女を登場させるということ自体が、無理だよ。ということに!
…なんでだ。理不尽だ。注目しないでくれ。
古い下水管に詰まった汚水になったよな気持ちで、出口求めてもんどり打つわたくし。10歳で初潮を迎え、身長の伸びは早々に停止、バレエ教室では指導者から「そろそろブラジャーをしたほうがいいですよ。」などと指摘され赤面、変成する我が身恥ずかしく腹も立ち、夜な夜な読書フィーバー、視力もどんどこ下がるよ。というご年代。
通俗性ばかり振りまきやがって、どうあっても無名性を獲得できぬ、言葉のみがさにあらず、「女として生まれたという事実そのものも、同じことだ」と、峻烈に思ったわたくし。
しかし、女である。
まるっきりの男装で出席した卒業式も終わり、制服中学生となった。待っていたのはじつに屈辱的なスカートの刑だ、何かの咎か。女であるという事実を服装によって絶え間なく、学校敷地から往来から、表明して歩くのだね咎人は。
自分はそれまで温め持っていたアイデンティティのよな、巣のよなものを根こそぎブン取られた禿げ散らし雛鳥となった。これまで以上に「女」という言葉を敵視、生徒以外にわざわざ女生徒という語があるんは、生徒は本来男性であるのが基本だからか、ふざけろ。とか、「Man」に対しなぜ「Woman」なのだ、男が正式でなんか付け足したのが女か、長くなるのが気に食わん、とか。まあ、かくして女分類表記するためにこそ存在する、他に何の利便性もない、ぞろりとしたブザマな制服スカートはだね、帰宅すると階段の下で脱ぎ捨てられざま、毎回ちからイッパイ床に叩きつけられた、思い出すとお気の毒。
だって日本語の一人称には性別があるしね。
なるほど「私」は男女兼用だ、しかし男性には「俺」もあるわ「僕」もあるわ「わし」もあるわ「オイラ」もあるわ。わわ。男性諸氏はその時々、マウンティングしたいなーとか、母性本能くすぐったろかーとか、ちょっとインテリぶっちゃおうかなーとか、TPOで使い分ける一人称がいくつもあるという、ご親切。
どうなんだ「俺」に匹敵するだけの強さと傲岸さと竹を割ったよな爽快感を伴う、女性の一人称はないの、と思ったことがある。これまた排水口に詰まった糸くずのような心持ちでウンウン唸っても、ようやくひねり出たのは
「あたい」
ただ一語。「あたいは…」だと語尾は「…なのさ。」か。いつの時代で、どこの地域なんだか、色彩感覚と衣服の形が見たことないものに変わり、茫洋とした田んぼを眺めているわたくし。
ぬう、自分は女である。
そういや看護婦という呼称は廃止後久しく、「看護師」がようやく定着したのだね、通俗性の排除と乾いた無名性という意味でも、どしどし進めてもらいたい領域。しかしその舌の根も乾かぬうちに、山ガールやらカメラ女子などなどという「類型+女」造語の出現引きも切らず、どんどこ生まれちゃ流通してる。土台この世には男と女しかおらんのだし、数もほぼ半々だというのに、女が行う山登りや撮影という現場において、高地における天気の読み方やレンズ選び以上に「女」に注目ってどうなんよと思うけども、逆に言えばこの世に男と女しかおらんがために、いつになってもこうなのだ、女は男ありきの対義語であることを一向にやめない。
しかしだ、本当に男と女しかいないのだろうか。
なんでもFacebookなるSNSの本家US版では、プロフィール欄で50以上もの性別から自身に合ったものをカスタム選択できるそうだ。その中から自分のモヤモヤ感に合致しそうなものは以下だろうか。
「agender」、性自認がないこと。「bigender」、性自認が両性。「gender fluid」、性自認が流動的。「neutrois」、中性的。「non-binary」、男女の二分類に当てはまらない。「pangender」、すべての性自認を網羅。
…この他にも合わせて50もの「性別」を示しているたぁ、何たる細分化。それにしてもこれはほとんど哲学の領域で、選ぶことすら難しく、一体自分はどれなんじゃい、いずれも言い得ているようでいて、しかしいまひとつ決定打弱いジレンマ。だってそうだろう、自身の性について「定義することそのもの」を疑う論議もあるのだよ、なぜ決めなけりゃなんないの? という話。だからさぁ、むしろ「女」よ、もっとどうでもいい単語になりやがれ。
そしてついでに「私」もだ。
必要以上の公人感・改まった場でございという窮屈さ・ちょっとした謙遜とおもねり。男女の別は取り払われても、違う配慮が透けている…。
少なくとも英語の「I」や中国語の「我」にある徹底して構いつけぬ感じ、完膚なきまでの記号性、乾いた風は吹いてないわな。罠。
「I」や「我」のひと息でぶん投げられる感覚も「わ・た・し」には存在せず、3音節もの回りくどさ、最後に「し」をつけるという発音の煩雑…。
男女兼用でもあり、もっと何の粉飾も行わぬ素っ気ない、機械的な単語で一人称全国統一を果たせぬものか、と思うわたくし。案外「わい」が良いのではないかと密かに思ったり。
言葉ひとつにちまちま背景を刻みつけるご感性は、繊細でもあり同時にうっとおしい。物事の精度を高めたいんではなく、何も想像してほしくない時にはじつに邪魔になりますよ。ええ。
相手に対する立ち位置や関係性、こちとら場の雰囲気を正しく汲んでおりますよという良識やら、示唆したい優越やへりくだりをじっとりヌメヌメ忍ばせるというよな細けぇご芸当たるや。
たかが主語のくせに。
主語に倦む。