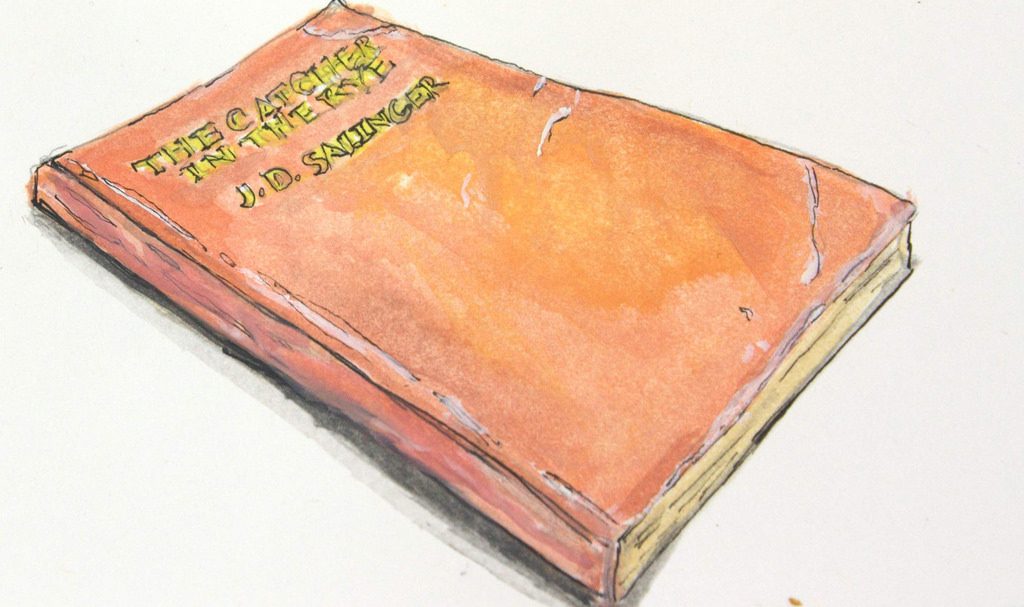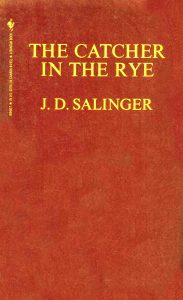photo by Rakka
「いつでも自分の好きな過去に戻してあげると言われたら、いつがいい?」他愛もない会話の中で持ち出される意味の無い質問だ。私には特に戻りたい時期はないが、戻りたくないのはいつかと聞かれたなら、迷わず高校生と答える。しんどくて、先が見えなくて、周りばかり気にしていた頃。中高生に戻りたいと答えられる人は、当時からポジティブで、リア充な青春だったのだろう。うらやましい。そういう人には多分この本は必要なかったはずだ。
『ライ麦畑でつかまえて』は、アメリカでの初版が1951年、以来青春小説の金字塔として読み継がれてきた。成績不良のため退学が決まった17歳のホールデン・コールフィールドが、衝動的に学校を飛び出し、クリスマス前のニューヨークをさまよう数日間の物語である。この邦題は1964年の野崎孝による翻訳版のもので、2003年の村上春樹による新訳版では原題のまま『キャッチャー・イン・ザ・ライ』となっている。村上版の方が内容に沿ってはいるのだが、この文章の中では長く親しまれた野崎版のタイトルを用いたい。
高校1年の時、理由は忘れたが、『ライ麦』を10代のうちに読んでおかなくてはならないと思った。ところが地元の書店を探して歩いてもなかなか見つからない。今のようにAmazonで簡単に手に入れることのできない時代の話だ。ある日、雑誌を探しに洋書コーナーに立ち寄った私は、赤い表紙に黄色い文字で『The Catcher in the Rye』と書かれたペーパーバックを見つけ、原書にチャレンジすることにした。
なんとかなると思って読み始めたものの、帰国子女でもない高校1年生の英語力で、口語調で書かれた小説を訳すのは難しい。特に俗語の類は私が持っていた学生用の辞書には載っていないからとても苦労した。”sonovabitch”の意味がわからず、困って英文科卒の父親に聞いたりしたものだ。それでも数ヶ月かけて、どうにか全文を読み通したのは、それだけの熱量が当時の私にあったからなのだろう。
(参考:当時買ったペーパーバックの表紙)
学校でうまくやれず、4度目の退学を控えたホールデンは、自身をとりまくほぼ全てのものに悪態をつきまくる。寮のルームメイト、教師、昔なじみのガールフレンド、ナイトクラブのウェイター等々。そんなホールデンに、学校では空気のように薄い存在感で、鬱憤を抱えて過ごしていた私は共感を抱いた。私の言いたいことを全部言ってくれる代弁者のように思ったのだ。そして、16歳という年齢でこの本に出会えたことに感謝したのだった。
若さは傲慢で不寛容なものだ。若さの前には道が無数に広がっていて、それがある種の全能感を与えてくれる。現実的に選ぶかどうかはともかく、可能性だけはいくらでも転がっているのだ。だがいいことばかりではない。選択肢が無数にあるということは、毎日何かを選択しなくてはいけないということだ。それが自分の未来を少しずつ形作っていく。友人に対しどう振舞うか、教師にどう接するのか。どの科目を熱心に聞き、どの科目で居眠りをするか。何かを選んで、それ以外を捨てる。なかなかにエネルギーのいることだ。それを生まれてからせいぜい十数年の経験と知識でやってのけないといけない。だから若者は周りを気にする。自分の選択が間違っていないという安心を得るために。
ホールデンが周囲の全てに難癖をつけ、唾棄するのもそのためだ。うまくやれない自分に内心は傷ついているのに、それを認めることから全力で逃げている。認めてしまうと、受け入れなくてはいけないことが次々に押し寄せてきて、それに耐えられないと知っているのだ。だから、大人の世界の全てをインチキと罵り、妹のフィービーや、病気で死んだ弟のアリーといった「子どもたち」を無垢なるものとして神格化する。自分をインチキな社会の枠組みの外側に置こうと抗うのである。
原題の『The Catcher in the Rye』は、本文中にこう登場する。妹フィービーに、「兄さんは世の中で起こること全てが気に入らない」と指摘され、いったいあなたは何がやりたいの、と聞かれてひねり出した答えだ。
(引用)「とにかくね、僕にはね、広いライ麦の畑やなんかがあってさ、そこで小さな子供たちが、みんなでなんかのゲームをしてるとこが目に見えるんだよ。何千っていう子供たちがいるんだ。そしてあたりには誰もいない――誰もって大人はだよ――僕のほかにはね。で、僕はあぶない崖のふちに立ってるんだ。僕のやる仕事はね、誰でも崖から転がり落ちそうになったら、その子をつかまえることなんだ」 野崎孝版より(引用終わり)
ライ麦畑の子どもたちが、崖から落ちてそのイノセンスを失わないように、たった一人の「わかってる」大人として彼らを救いたい、と言うのである。実際には、崖から落ちかけているのはホールデン自身であり、それを押しとどめているのはフィービーだというのに。
今となっては笑い話だが、高校生の私は若さに全幅の信頼をおいていた。若さこそが正義であり、大人になるということは純粋さを失うことだと、その頃の私は考えていた。ついでに白状すれば、30歳になった自分がつまらない大人になっていたら、その時はこの世界からさよならしよう、とか考えていた。それほど本気でないことくらい、自分でもよくわかっていたけれど。ああ恥ずかしい。だが若さなんて所詮そんなものである。
当時の私に教えてやりたい。30歳なんて全然大人じゃない。少なくとも私はそうだった。 そもそも大人になるというのはどういうことなのか。社会的には、親から自立した生活を営むようになれば大人なのかもしれない。では精神的にはどうなれば大人なのだろう。『ライ麦』のホールデンや、高校生の私が考えていたように、大人は欺瞞の中で生きているものだろうか。私は大人になったのだろうか。
『ライ麦』の後半、家にも帰るに帰れず、手持ちの金も底をついたホールデンは、以前通っていた学校の教師、アントリーニ先生を頼る。ホールデンの現状を憂う先生は、精神分析学者ウィルヘルム・シュテーケルによる一つの言葉を書いて渡すのだ。
『未熟な人間の特徴は、理想のために高貴な死を選ぼうとする点にある。これに反して成熟した人間の特徴は、理想のために卑小な生を選ぼうとする点にある。』
ホールデンはありがたく受け取るが、この言葉にはピンときていない。高校生の私にもあまりピンと来なかった。しかし今の私には、自分の身にあてはめて理解することができてしまった。それを成熟と呼ぶかどうかはともかく。
高校の時以来、つい最近まで私は『ライ麦』を読み返したことがなかった。読んでどう感じるのか、なんだか怖かったのだ。自分の中で何かが決定的に失われたと感じたくなかった。だが思い切って読んでみたら、何かが失われたというより、むしろ加わったと私は感じたのだった。
10代で読んだときは、ホールデンが切り捨てる様々な「インチキ」な事柄の大部分に共感していたが、今読み返すとホールデンが断罪する事柄にも様々なレイヤーがあることに気づく。何より、ホールデン自身の虚勢や混乱が手に取るようにわかるようになったのだ。
若さの前には無数の選択肢があると、先ほど書いた。初めは特に意識もせず、好きに何かを選ぶだけだが、そのうち目の前の道がかつてのように多くないことに気づく。ひとつの道を選べば、選ばなかった道は消えていく。私くらいの歳になれば、道はほぼ1本道だ。これまでの選択には覚悟のいるものもあったし、後悔もあった。そして何度も恥をかいた。大人になるのは、恥をかき慣れることではないかと思う。若いときは、自分だけが恥ずかしく、自分だけが孤独だと思っていた。けれども、人は誰でも恥をかくし、孤独なのだ。それを知ることで大人は作られていく。そして選べる道が減っていくのと引き換えに、より細部まで見渡せる眼を手に入れるのだ。
例えるなら、解像度のようなものだ。若いときに見えていた世界がファミコンのドット絵だとしたら、経験を重ねアップデートされた世界はPS4の画面になる。若さのせいで単純化されていた世界の輪郭が、また違った形に見えてくるのだ。その中で、イノセンスは重ねられたレイヤーの奥に隠されていく。大人の世界は欺瞞でできているのではなく、私がそのレイヤーまで見通す力がなかっただけかもしれない。
『ライ麦』を発表した後、サリンジャーはコネチカット州の田舎町に移り住み、1965年に『ハプワース16,1924年』を出版したのを最後に、2010年に亡くなるまで新刊を出すことはなかった。自宅の周りに2メートルの高い塀を張り巡らせて、世捨て人のように生活しているなどと噂はあったが、実際には地域にそれなりに溶け込み、平穏な暮らしぶりだったそうだ。
作品を発表しないというのは、作家としては「死」を意味するとも言える。彼が選んだ生き方が、はたして「高貴な死」としてなのか、それとも「卑小な生」だったのか、私にはわからない。長年の隠遁生活の間にサリンジャーが残した原稿があると聞いた。いつか出版されるなら、彼が世界の中の「インチキ」とどう向き合い、自身のイノセンスをどう守ろうとしたのかを、私は読みたい。